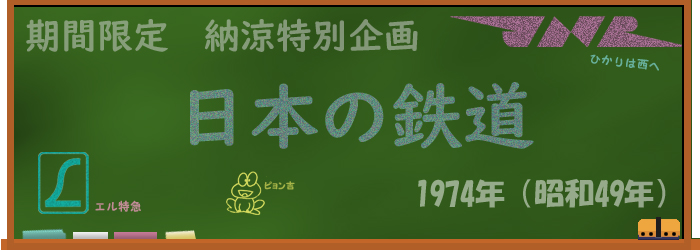北陸本線
特急列車(昼行)
特急「北越」
481系
(大阪〜新潟)
L特急「雷鳥」
481系
(大阪〜富山)
L特急「しらさぎ」
481系
(名古屋〜富山)
北陸本線は60Hzの交流電化なので、交直両用電車が使われます。都会側の起点が大阪もしくは名古屋となるため、必ず直流の東海道線を走るからです。
分岐駅である米原駅は、大阪からのルートが正方向となり、名古屋からの列車は進行方向が逆になります。
L特急「しらさぎ」
581・583系
(名古屋〜富山)
○
コキフ50000形
○
特急「しらさぎ」のうち1往復は、南福岡電車区所属の581・583系が担当します。これは東海道線の特急「金星」の間合い運用で、国鉄ならではの広域運用ですが、夜行寝台と昼行座席とを兼用する581・583系だからこそできる効率運用でもあります。
特急列車(夜行)
特急「つるぎ」
20系客車
(大阪〜新潟)
急行列車
急行「立山」
471系
(大阪〜糸魚川・宇奈月温泉・立山)
急行「ゆのくに」
471系
(大阪〜金沢)
急行「越後」「ゆのくに」
急行形気動車
(大阪〜新潟・輪島・珠洲)
北陸本線の急行列車のヘッドマークは、この時は幅の広いものをつけていましたが、併結するときの取り外しの問題からか、しばらくすると貫通路に収まる幅の狭いものに変わります。
急行「兼六」
471系
(名古屋〜米原〜金沢)
急行「くずりゅう」
471系
(米原〜金沢)
急行「大社」
急行形気動車
(名古屋・金沢〜敦賀〜出雲市・大社)
急行「大社」は、北陸本線から小浜線、宮津線を経由して山陰本線に向かう急行で、北陸本線の起点が2方向別々に存在し、敦賀で両方向を併合し、山陰方向に向かうのです。同じ「大社」でも北陸本線内では敦賀から北と南では時間帯の異なる別列車です。また、名古屋発着の列車は、米原、敦賀、豊岡の3か所で方向転換するという特異な列車でもあります。
普通列車
快速列車
471系
(福井〜富山)
普通列車
旧型客車
(米原〜直江津〜長岡)
○
○
○
敦賀第二機関区・米原機関区
電気機関車
ED70
(田村〜糸魚川)
電気機関車
EF70
(田村〜糸魚川)
ディーゼル機関車
DD50
(米原〜田村)
北陸本線の直流交流のデッドセクションは、米原の隣りの坂田〜田村間にあり、この区間を越える列車はディーゼル機関車が牽引していました。田村駅からは交流の電気機関車が牽引します。
1975年に北陸本線の主要列車が湖西線経由になると、交直両用のEF81形電気機関車が投入され、これらの機関車は用途を失います。
湖西線
新快速
153系
(姫路〜京都〜堅田)
普通列車
113系700番代
(京都〜近江今津〜永原)
普通列車
急行形気動車
(近江今津〜敦賀)
琵琶湖の西側を走り、京都と北陸本線とを短絡する新路線の湖西線は、1974年7月に開通しました。寒冷地を走るということで、半自動扉を装備した113系700番代が新造され、東海道線の新快速も乗り入れています。
ただ、北陸本線の特急、急行列車の運行は、1975年3月のダイヤ改正まで持ち越され、この時点では高規格の線路を走るのはローカル列車だけでした。
なお、永原〜近江塩津間に交流直流のデッドセクションがあるため、永原以東の列車は、北陸本線の気動車が担当していました。

越美北線
普通列車
一般形気動車
(芦原温泉〜福井〜九頭竜湖)
○
ワ12000形
○
七尾線・能登線
急行「能登路」
急行形気動車
(金沢〜輪島・蛸島)
普通列車
一般形気動車
(金沢〜輪島・蛸島)
富山港線
各駅停車
72系
(富山〜岩瀬浜)