中央西線・篠ノ井線(名古屋〜長野)
特急列車
L特急「しなの」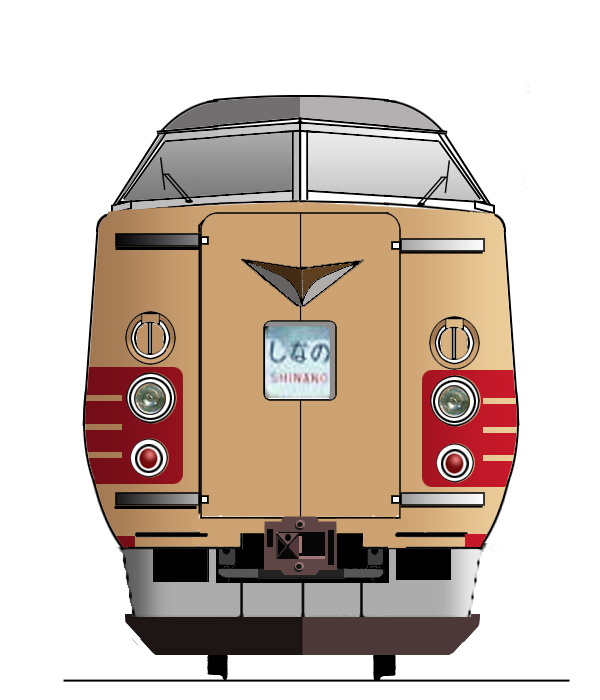
381系
(名古屋〜長野)
L特急「しなの」
キハ181系
(大阪〜名古屋〜長野)
1973年7月の中央西線全線電化と同時に、特急「しなの」には振り子式の381系電車が投入され、名古屋〜長野間を3時間20分と、ディーゼル特急に比べて40分もの時間短縮を実現しました。ただし、この時点ではまだディーゼル特急も残されていました。
急行列車
急行「きそ」
165系
(名古屋〜長野〜直江津)
急行「ちくま」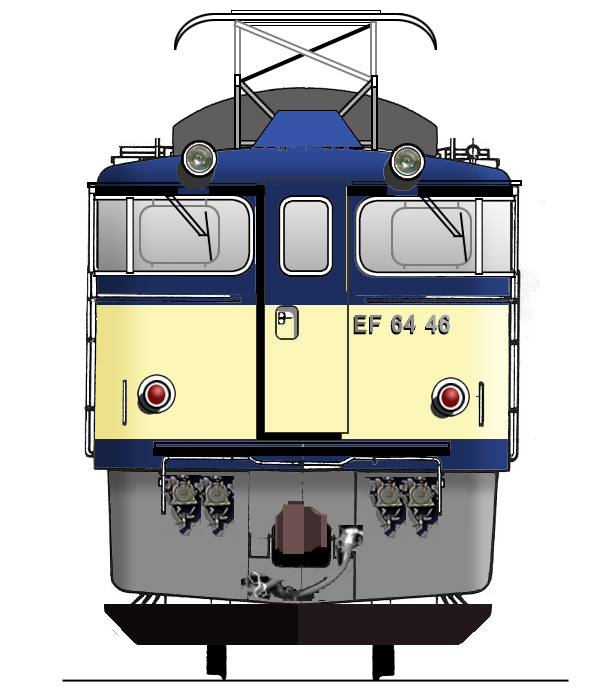
旧型客車(座席)
(大阪〜長野〜妙高高原)
急行「赤倉」
キハ58ほか
(名古屋〜長野〜新潟)
中央西線の急行列車の代表3車種を並べましたが、「きそ」は昼行・夜行取り混ぜて電車、気動車、客車のどれもが走ります。大阪発着の「ちくま」は夜行列車のみの設定ですが、客車、気動車が存在します。そして新潟に行く「赤倉」は全線電化区間を行く急行ですが、気動車がその任に当たります。
普通列車
快速
113系
(名古屋〜中津川)
快速「木曽路」
159系
(名古屋〜木曽福島)
中央西線にも113系が投入され、専ら快速列車に使われていました。
季節運行の快速「木曽路」には、修学旅行用の「こまどり」用務を追われた159系が投入されます。そのまま塩尻まで足を延ばし、ついでに中央東線の急行「アルプス」になって新宿まで行くこともあったようです。
普通列車
80系
(名古屋〜中津川〜長野)
普通列車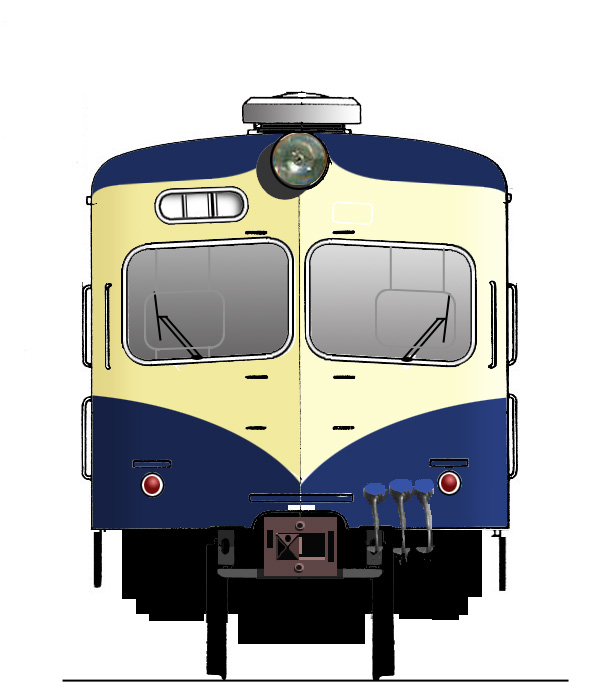
70系
(名古屋〜中津川)
普通列車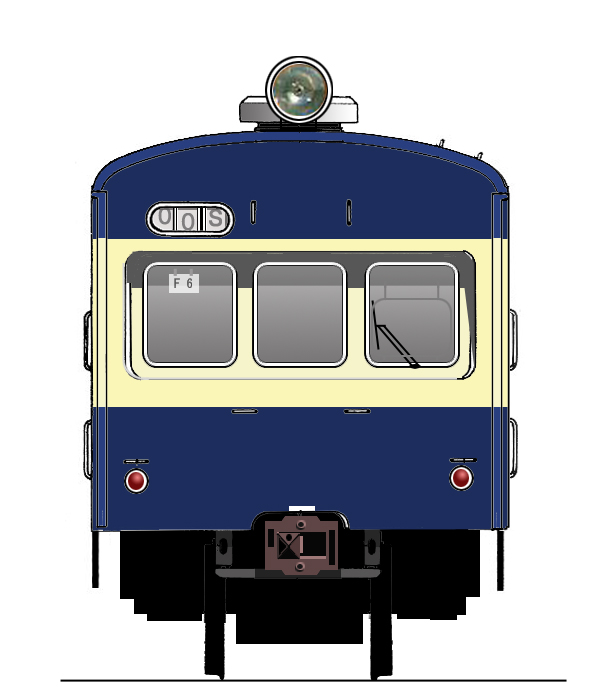
72系
(名古屋〜釜戸)
戦後型旧性能電車3兄弟が走る中央西線。2扉の80系は長野まで足を延ばし、ついでに中央東線甲府までの運用があります。3扉の70系は中津川までの中距離運用、4扉の72系は名古屋近郊の都市圏輸送を専ら担当します。運行区間の長さと扉の数は反比例します。
太多線
普通列車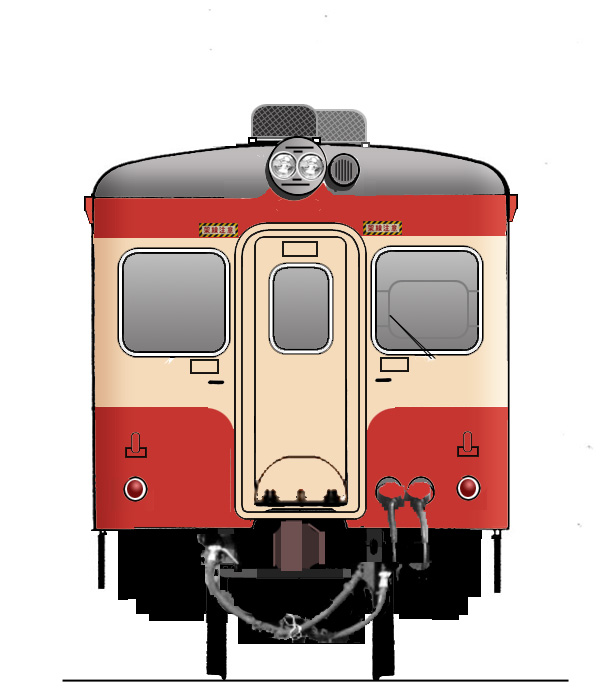
一般形気動車
(名古屋〜多治見〜美濃太田)
明智線
普通列車
一般形気動車
(中津川〜恵那〜明智)
長野運転所
振子・連接車体試作車
591系
(留置)
ディーゼル機関車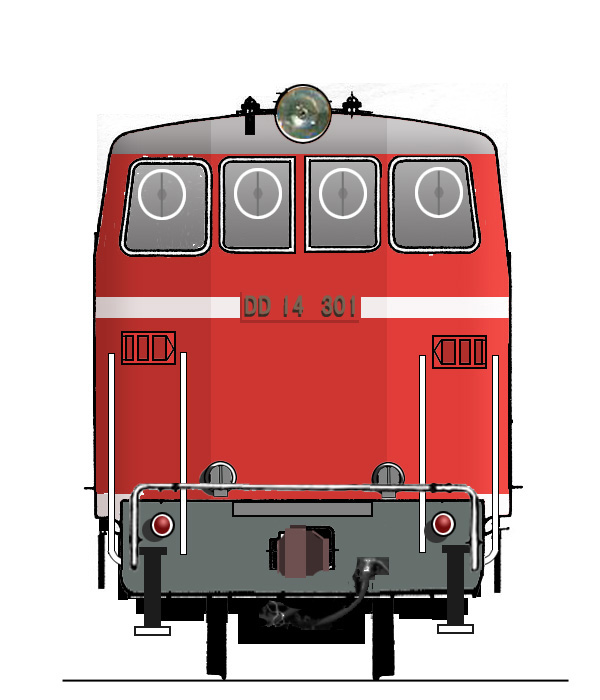
DD14
(除雪車・入換車)
救援車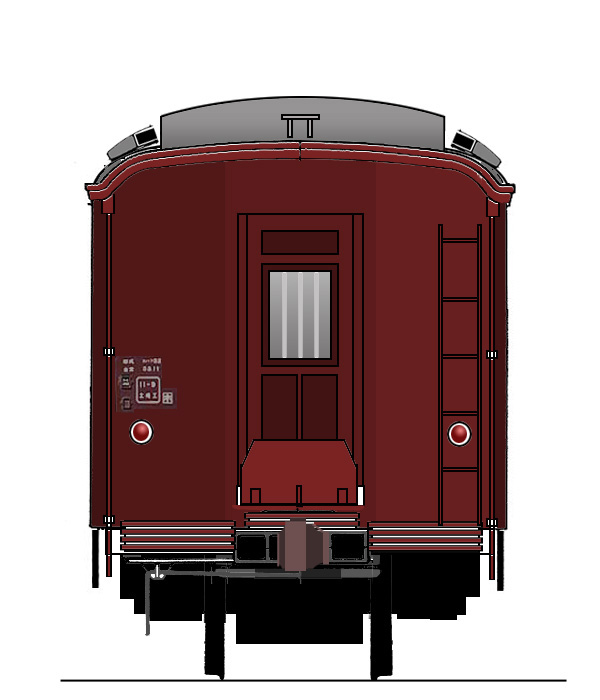
スエ30
(長野運転所)
長野運転所には、1970年に試作された振り子式の591系が留置されていました。この車両の振子機能、軽量車体などが特急「しなの」381系に生かされています。
ディーゼル機関車のDD14は、除雪用ロータリーをはずした夏用の姿です。L字形の独特のフォルムを持つ機関車で、こちら側に付属のロータリーをつけると、勇ましい除雪車に姿を変えます。
※591系は、留置時点では前面の愛称幕は抜かれていましたが、ここでは試運転時の姿を再現しました。

私鉄線(沿線)
東濃鉄道駄知線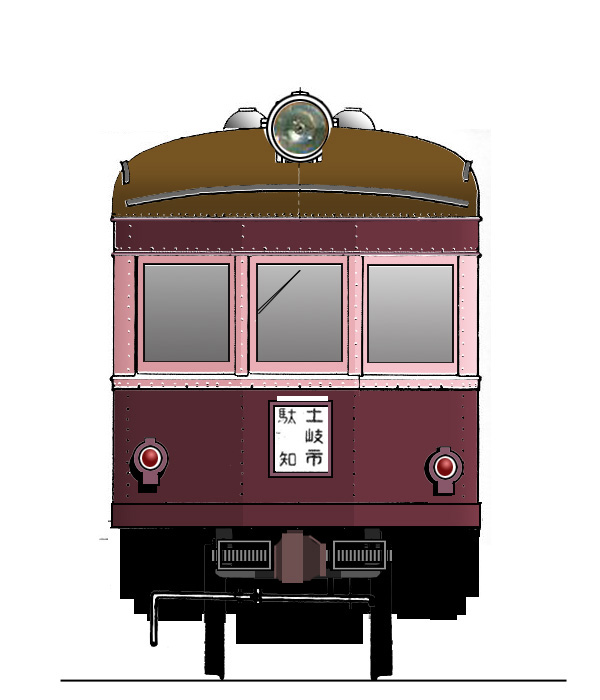
モハ110形
(土岐市〜東駄知・運休中)
北恵那鉄道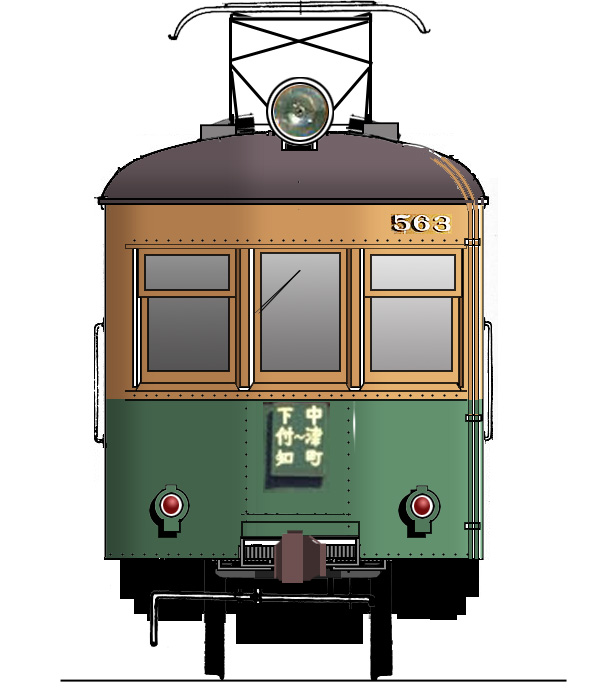
モ560形
(中津町〜下付知)
松本電鉄上高地線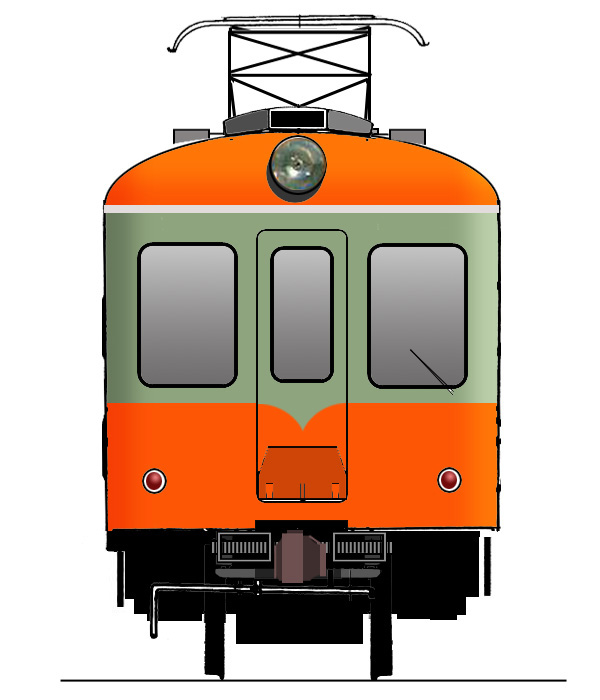
モハ10形
(松本〜新島々)
中部地方の私鉄というのは、鉄道にしろバスにしろ、地味で独特な色使いが多いと感じていました。

