もし「紀行文を書いてよ」と頼まれたら、どんな紀行文を書けばいいんだろうか。実際に頼まれたわけではないのだけれど、ちょっと心配になってしまったので試しに書いてみました。
(第8回)駅弁コンプライアンス大会
東京駅とか大宮駅とかのエキナカにある銘店街で、すき焼きとかステーキとか牛タンとかの弁当を買って、ホテルで食べたり、家に持って帰ったりするのがマイブームになった。その話をしたとき、「駅弁て食べないんで」みたいなリアクションをする人が何人かいた。エキナカの弁当って駅弁なのか? 多分違う。エキナカの弁当はデパ地下の弁当に近い。名の知れた有名店が作っている。
エキナカの弁当が駅弁なら、ホームにあるコンビニの弁当も駅弁か。市中にあればコンビニ弁当なのに、駅構内にあるだけで駅弁か。多分違う。
JRが公認した弁当で、駅弁売店で売っていたりするのが、駅弁なんだと思う。
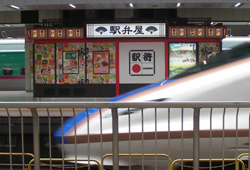 そんな駅弁に対して、「高いし、冷めてるからおいしくない」とか否定的な発言をする人も多い。
そんな駅弁に対して、「高いし、冷めてるからおいしくない」とか否定的な発言をする人も多い。高いのはしょうがない。非日常なのだから。食材も特別なものが多いし、売るための所場代も取られる。でも、デパ地下よりはちょっとは安い。
冷めてるのは、弁当なんだから当たり前のこと。学校で昼時間になって蓋を開ける弁当は、だいたい冷めていた。
弁当が暖かい状態で食べられるようになったのは、1980年代にオープンキッチンの作りたて弁当屋さんが登場してからだと思う。
そして、コンビニで弁当が売られて、お店の電子レンジを使って温めてくれるようになって、弁当というのは暖かいのが当たり前になって行った。
そんな便利な世の中で、駅弁は冷めても食べられるように作られている。むしろ、冷めてるからおいしい。それに、列車の中で食べられるように、匂いとか汁とかが出ないように作られている。だから、本当は、移りゆく景色を見ながら、列車の中で食べるのが一番おいしい。そういうシチュエーション料理なのだ。
しかし、残念ながら、1980年代までに駅のホームでの立ち売りは姿を消し、21世紀になったら車内販売さえも激減した。
さらに最近気になるのは、レジで必ず消費期限を伝えられることだ。
 その兆候は、しばらく前から始まっていた。
その兆候は、しばらく前から始まっていた。コンプライアンスという言葉が出始めの頃、特急「しなの」の車内販売で、積んである駅弁を売ってもらえなかったことがあった。2時間後ぐらいに消費期限が来るからだという。でも、今なら食べられるし、1時間後に終点に着いた後でも食べられる。なのに売らないという、行き過ぎたコンプライアンス遵守だった。
小淵沢駅の「高原野菜とカツの弁当」も、さっくりしたチキンカツにシャキシャキの生野菜が入った魅力的な駅弁だが、今は小淵沢駅でしか買えない。遠くに運ぶと悪くなっちゃうかららしい。一時期は、予約しないと買えないことさえあった。行きに寄ったら予約制だったので、翌日の帰りに寄ることにして予約した。そこでついうっかり「予約の時間に少しくらい遅れてもいいですよね」と余計なひと言を口にしたばかりに、「それは困ります」と予約を取り消されてしまった。今の一言で、時間通りお渡しできない可能性が生じたので、再予約も受け付けられないと言う。
行き過ぎたコンプライアンスは、モンスター・クレーマーの存在が原因だとは思うが、売りたくないなら買わない、と決めてしまう人もいるだろう。百貨店の駅弁大会では行列を作ってまで買うのに、駅にある駅弁売店には見向きもしないという、本末転倒の風景が、当たり前になりつつある。
(画像はほぼイメージで、本文とは関係ないものがほとんどです)
(つづく)

